2017年2月も終わる頃、わたしは【オンライン起業家】の養成講座を始めようかと思い立ちました。
私は2015年4月の独立以来、個人起業家としての集客活動のほとんどをWEB上、つまりオンラインに集約させてきました。
その理由のひとつには地方在住で、都内の方のように動けないというのもありましたが、それ以上にWEBの世界、オンライン、ネットの世界の可能性の素晴らしさに魅了され続けている背景があります。
今日はその【オンライン起業】の魅力も伝えつつ、実践的ですぐに役立つノウハウなんかもお伝えできたらと思っています。
本日もどうぞ、よろしくお願いします。
本日紹介するWEB集客ツール

WEBを使って集客するためにはいくつかのツールをまず紹介しなければいけません。
ホームページ、ブログ、フェイスブック、LINE、などなど。私が日頃活用しているツールと、かんたんな利用目的をまずはお伝えしたいと思います。
ワードプレスブログ

自分の思い通りにカスタマイズし放題で、SEO(検索)にも強いと言われるワードプレス。
よく無料のブログサービス(はてなブログ等)と勘違いされますが、ワードプレスはあくまで【ブログソフト】なので、ドメイン(URL)とサーバーは自分で用意する必要があります。
自分をブランディングするためのメイン集客ツールになります。
アメーバブログ(アメブロ)
サイバーエージェントさんが提供する、商用利用不可の無料ブログサービス。
ブログというものの、その実態は限りなくSNSに近いため、読者登録やイイね!などを活用することで、ブログを始めたばかりの初期からアクセスを集めることができます。
かつてメインツールだったアメブロですが、今もサブで現役活動中です!
フェイスブック

言わずとしれたSNSの代表格のひとつ、フェイスブック。
長文の投稿、写真投稿、動画投稿、グループの作成、ファンページの作成、イイね!やコメントでの交流。そして、無料の音声通話やビデオ通話ができてしまうメッセンジャー機能などなど。
これひとつでも集客が十分可能な強力SNSツールです。
ツイッター
SNSと言えばツイッターを最初に浮かべる人は多いかもしれませんね。
とにかくタイムリーなネタに強いツイッターは、ハッシュタグなどを活用した拡散性やニュース性においても注目度ナンバーワン。
個人起業家にはちょっと集客として使いづらい一面もありますが、活用法は十分にあります!
インスタグラム
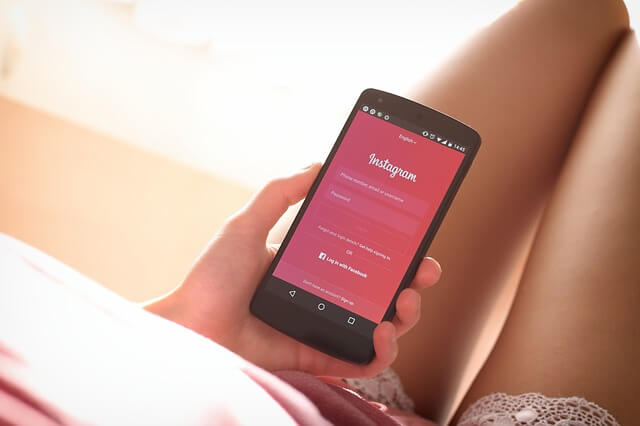
オシャレな写真投稿がメインのSNSで、動画機能や複数枚写真の投稿、ハッシュタグなどが使えます。
主に物販系、お稽古サロン系のお仕事、または飲食店で集客力を発揮するSNSツールですが、セラピストの方でも集客を成功させていたりと工夫の余地がまだまだあるツールです。
YouTube
誰もが知っていると言っても過言ではない動画配信サービス。
全体公開、限定公開、非公開などの分類分けをして投稿ができたり、オンライン上の編集画面で簡易な調整ができたりと、無料とは思えないクオリティの高さを誇るサービス。
文章や写真、短い動画では伝えきれないコンテンツを配信するのにピッタリです。
メルマガ
無料のものから有料のものまで、種類豊富に様々なものがあります。
別名で【ニュースレター】と呼ぶ人もいますが中身は基本的に同じです。興味のある方はEメールアドレスを登録し、そのアドレスで情報やお知らせを受け取る仕組みです。
用途は主に2つで、既存のお客さまのリピートを促すフォローとしての役割と、新規で登録してくれた方への価値教育、ファン化が目的です。
LINE公式アカウント
商業版のLINEと考えてもらって大丈夫です。
機能としては、登録時やキーワードに合わせた自動返信や1:1モードで直接LINEのやりとりを個別に行うこともできます。
メルマガに比べて開封率が高いことから注目の媒体のひとつです。
Wix
無料のホームページ作成サービスの1つ。
他にもJimdo なども同様のサービスを提供していますが、デザイン性という意味で私はWix を推奨しています。
カスタマイズの自由度も高い上、初心者でも直感的に操作が可能です。
ペライチ
無料のセールスレター作成サービス。
え? セールスレターって何? という方もいるでしょう。いわゆる1枚ペラの縦に長いウェブサイトのことで、主に商品の紹介に使われる形式です。
ネット広告をクリックすると、たいてい縦長のセールスページに飛ぶので、ぜひ今後は意識してみてください。
フォームズ
オンラインの無料お問合せフォームです。
他にも「フォームメーラー」社も同様のサービスを展開していますが、個人的に使い勝手はフォームズが便利なのでこちらを推奨しています。
ZOOM(ウェブ会議室)
遠方の方と仕事をする際に非常に便利なので、打ち合わせやミーティング、コンサルティング業務では重宝します。
有料のプロ版にお申込みをすると、多様なサービスを受けることができます。通信量も少ないので回線が安定している他、お客さまにURLを送るだけでOKなのも魅力です。
IDをクリックしてもらうだけでビデオ通話に自動的につながるのでIT機器が苦手なお客さまを相手にする場合に特に有効です。
組み合わせて事業展開

ここまでにご紹介したオンラインツールは、WEB集客はもちろん、お問合せの受付から実際のサービス提供、フォローの仕組みなども含めて運用が可能です。
王道のものから少し応用を入れた使い方を含め、2パターンのやり方をまずご紹介したいと思います。
基礎編 ①
アメブロ×リザーブストック、の組み合わせをご紹介します。
もっとも王道であり、講師・コンサル・コーチ業をしている人であれば一度は考える王道の組み合わせの1つです。
アメブロはブログサービスの1つですがSNS要素が強いため、見込み客の少ない起業初期の方であれば早期にアクセスを集めることが可能です。
つまり、自分から読者申請をしたり、イイねやコメントを付けることで自分のブログに関心を持ってもらうキッカケが作れるからです。
アメブロを使って読者がある程度集まったら、無料のメルマガにご案内します。そこで使えるのがリザーブストックです。
かつてのmixi のように招待制ではありますが、無料の範囲で様々なことができます。例えばメルマガ配信やステップメール機能、ファストアンサー、イベント受付、名刺管理、などなど。
聞き慣れない機能もあると思いますが、個人起業家にとっては必須の管理システムが揃っています。
アメブロ→メルマガの流れを作ったら、あとはメルマガ内で商品の販売を行い、購入してくれたお客さまには引き続きメルマガを送り、リピーターになってくれるようにフォローの体制を組めます。
ただしひとつ注意なのは、アメブロは【商用利用禁止】ですので、アメーバ運営サイト側のさじ加減ひとつでいつでも記事が削除、もしくはブログごと削除される怖れがあります。
そこに抵抗がある場合には【はてなブログ】もお勧めです。はてなブックマーク機能を含め、交流の仕組みがある程度揃っています。
ただし大事なのは「どこにお客さまがいるか?」ということです。
講師・コンサル・コーチの人がアメブロをこれまで使い続けてきた経緯があるため、それらのスモールビジネスに関心がある人を対象にビジネスをするのであれば、アメブロの使い方は視野に入れる必要はあると思います。
基礎編 ②
フェイスブック × LINE の組み合わせでの展開方法です。
ブログと違ってフェイスブックの個人アカウントは検索で見つけてもらうことはできませんが、その代わり「友達申請」や「イイね!」「コメント」「フォロー」などの機能が揃っています。
友達の数が1000人を超えている人はたいていビジネス仕様と捉えて良いと思いますので、まずはイイね!やコメントなどの交流を続けながら、少しずつ友達の数を増やすと良いでしょう。集客を可能にする目安は友達の数が1000人を超えたあたりです。
フェイスブックで繋がった方々のうち、あなたのサービスに興味がある人がLINE に登録してくれるように促しましょう。まずはLINEの登録者数を100人を目安に頑張ります。
普通のLINEのやりとりをするように、見込みのお客さまと関係を築いていきましょう。
もちろんこちら側からの一斉送信機能もありますので、読者の方に役立つ内容を配信することも必要です。
この際、LINEでの長文は嫌われますので、YouTubeで撮影した動画のURLや、チラシを圧縮した画像などを添付するなどの工夫をすることで、短文でも説得力のあるメッセージが作れます。
LINEから告知記事に最終的には流して、そこでサービスの購入が行われればミッションクリア! この際の告知記事は、ペライチなどのセールスページ専用サイトを活用すると良いでしょう。
引き続きお客さまをLINEでフォローしていきます。
応用編 │ 実例付き
これは私の実例ですが、まずはメインブログに読者の方を集める工夫をします。
ブログに読者が流れてくるルートは大きく分けて2つで、1つは【検索】で見つけてもらう場合で、2つめは【SNS経由】でブログを見つけてもらう場合です。
ブログ記事を毎日2,000~4,000字のペースで更新し続けると、100記事を超えたあたりから【検索】で見つけてもらいやすくなります。もちろん漠然とした記事内容ではなく、読み手にとって必要な情報が網羅されている必要はあります。
SNSのアカウントも事前に育てておく必要があるので、フェイスブックとツイッターを中心に「友達」や「フォロワー」を増やし、あなたの投稿に関心を持っている人を増やしておきましょう。
SNSアカウントの王道の育て方として、2つの意識するポイントがあります。
① お役立ち内容
② 共感内容
自分が発信したいものを投稿するだけでなく、読み手にとっても有益な情報を含んだ投稿を意識しましょう。もし人気カフェに行ってすごく混んでいたら、
「人気カフェだからさすがにお昼前には混んでました! もしこれから行く人はオープンの10分ぐらい前から並ぶと確実かも!」
みたいに自分の個人的な想いと共に、お役立ち内容を含ませます。
共感記事に関しては、自分の心の変化を綴ると共に、具体的にそれがどういう経緯だったのかも書きます。
「すごく不安だったけれど、私、変われました!」だけに留めず、
「初めての出産、初めての育児、初めての起業。。不安なことだらけだけど、毎日ブログも書いたし、何より月売上100万円をキープしながら家族とも仲良くできています。私、変われたかもって今なら思う。自分で決めたことをやり抜けたから」
みたいに書くようにすると良いですね。
このような流れで【検索】からは情報を求めている濃い読者が集まり、【SNS】からはあなたの人柄に共感した読者がブログに集まってきます。
そのブログの中で、さらに濃い情報、さらに共感する記事を書き続けることで、あなたのメルマガやLINEにも興味を持ってくれるようになることでしょう。
メルマガは一方的な情報発信になりがちですが、LINEはつながりが濃密です。
そのあたりの特性を活かしながら、まずは無料や低価格のものから【接触】できる機会を増やし【ヒアリング調査】つまりアンケートなどを取っていきましょう。
お客さま候補の方々があなたに求めることが見えてくるので、そこから【商品アイデア】の種が生まれます。
その商品アイデアを形にし、実際にメルマガなどで販売していきましょう。
実際のサービス提供の際にはZOOM などのビデオ通話サービスを取り入れることで自分の時間を有効に使うこともできるでしょう。
ざっくりとここまでをまとめると、
検索&SNS →ブログ →メルマガ&LINE → ZOOM でサービス提供、の流れです。
色々なオンラインツールを使えば良いというわけでもないので、自分にとって集客効果の高い有効なツールのみを採用してください。そのためにも、ビジネスの原理原則を学び、それに沿ったツールの目的を理解することが必要です。
応用編の実例
ある人が、たまたまフェイスブックで流れてきた私の投稿を読み、感動し、ブログも読んでくれました。
そのブログを読み「これは私のことだ!」と思い、すぐさまLINEに登録してくれました。
LINEでは1:1モードで会話ができますので、ブログがとても勉強になりましたと感想が送られてきました。
私は「もしその内容にご興味がおありなら、まさに今日その内容についてメルマガを書いたところです。再送しましょうか?」と伝えました。
そしてさっそくそのメルマガを読んでくれた方は感動してくださり、メルマガの巻末についていた「起業相談」にお申込みをくださりました。
ここまでの流れ、わずか半日です。
まとめ

ここまでの内容で、一貫していたビジネスの原理原則が1つだけあります。お気づきでしょうか?
それは【集めて売る】という考え方です。
ブログを書いて商品案内を書く。
ホームページを毎日更新して商品が売れるのを待つ。
というスタンスではないということです。
売り手であるこちら側から、商品を売り込むことなく有益な情報やサービス、またはイイねやコメントを先に【与える】ことで、あなたに興味のある人が【集まる】という現象を作ります。
そして集まって方々に対してどんなものを求めているのかというニーズを実際に聞くようにして、売れそうだと判断したものを商品化して【売る】ということをします。
これが【集めて売る】というオンライン起業家には必須の考え方です。
様々なSNSやオンラインツールが溢れている世の中ですが、どうすればそういったツールを使いこなしながら【集め】、そしてお客さまの側から「買わせてください」と言われる状況を作れるか。
それを考え続けるのがオンライン起業家の活動になります。
驚きなのが、これらはかつて数億円をかけなければ企業側も使えなかったようなシロモノばかりです。今は個人がそれらを無料で使える時代なのです。
その恩恵を受けているにも使わないのは、私はとってももったいないと思っています。
21世紀の現代において、なぜ20世紀の働き方をあえて持ち込む必要があるのでしょう?
私たちは21世紀に生きているにもかかわらず、先代からの20世紀の働き方が頭にインプットされ、過去の枠組みに囚われてしまっている状態にもあることを知ると、これからの働き方が違って見えてくるのではないでしょうか?
古さの中にある良きモノは引き継ぎ、新しい時代には新しい時代の働き方を。
さあ、あなたは今日から何する?











