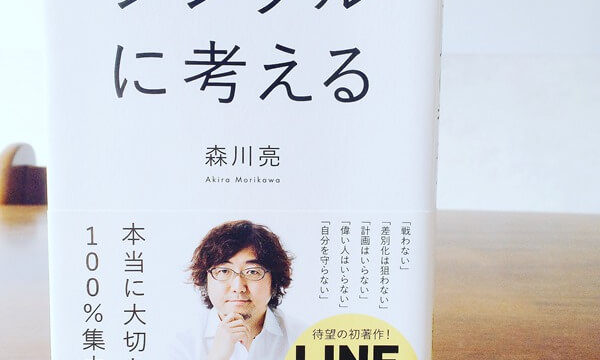2017年10月24日。
わたくし大崎博之は、おかげさまで36歳の誕生日を迎えることができました。
今年はとにかく葛藤が多い年で、人生の中でこれほどまでに自分の内面を見つめたのは大学3年次の就職活動以来かなと思っています。
何に思い悩み、何に希望を見いだし、これからどこへ向かおうと考えているのか。
そういった想いの記録をここに残そうと思います。
起業ブームやバブルが生み出したもの

1つのノウハウが、ここまで大きなお金を動かすところを間近で見てこれたのはとても貴重だったなと思っています。
SNSが浸透し、その中でも【アメブロ×Facebook】というのは本当に大きなマーケットを作り、女性起業家という心象が人々の心に埋め込まれていく。
そして、そのバブルがはじけていく様子、ブームが去っていく流れの中に身を置くことの怖さのようなものも一緒に体験してきました。
私はノウハウというのはビジネスにおいてキッカケにはなるけれど、永続的に使えるものではないと考えていました。
日本の武道の世界にある【守破離】の考え方でいうと、ノウハウというのは最初の【守】の部分だなと最近思うようになっています。
つまり、自分に合おうと合わまいと、まずはその型通りにノウハウを実践してみることが大事。その中でもうまくいくこともあれば違和感を覚えることもある。
そこから自分の頭で考えられるようになり、やがて【破】のステージへと進む。

ただ少しやっかいだったのが、守破離の【守】であるノウハウが、あたちこちらで乱立し、時にはどこまでいってもノウハウが終わらないような、そんな感覚さえあったこと。
それでも、
- 起業初期の認知・新規集客ステージ
- 起業中期の売上・顧客化ステージ
この2つのステージでやるべきネット起業のノウハウ、起業女子ノウハウはある程度決まってくるものがあり、それだけでも年商500~1000万円というのは十分に現実的なものでした。
そんな中、起業のバブルが弾け、ブームが去っていくと、時代の後押しというものがなくなり、厳しい起業環境だけが残るようになりました。
つまり、着実にコツコツと、ビジネスの原理原則を守れる人だけが生き残ることができるような、至極当たり前の世界が到来したのです。
私が尊敬する経沢香保子さんはTwitterの中で次のように言及しています。
成功にはタイムラグが必ずある。
成功には順番があって、自分が先に得たい、自分ばかり見て急ぐではなく、
まずは、周囲に与えること。楽しませよう、幸せにしよう、よい提案をしよう、信用を積み重ねることがファースト。
つまり、まわりを成功させることができたら、自分が成功するという順番。— 経沢香保子@1h1000円〜キッズライン (@KahokoTsunezawa) 2017年10月21日
なので、ツイッターやソーシャルなど、SNSで成功しようと思ったら、芸能人でないかぎり、自撮りより、有益な情報発信の方が最終的に上手くいきそうだし
起業しようと思ったら、徹底的に周囲に貢献することが先。
相手を先に喜ばせることができる、サービス精神旺盛な人が生き残ってる気がする。— 経沢香保子@1h1000円〜キッズライン (@KahokoTsunezawa) 2017年10月21日
女性起業の世界では、それぞれの『コミュニティ』の中で売り買いするのがやがてスタンダードになりました。
商品設計やセールス、ビジネスモデルの話よりも、集客をいかにどうするかが起業立ち上げ期の問題であり、そこを『コミュニティ』の力を使って、仲間内で売り買いすることで販売実績を作り、そしてそれを元にプロモーションする…
どうにも変な世界だったわけです。
その世界では、周りの人に貢献し、まず他人を幸せにすることで、やがて成功が時間差で自分の手元にやってくるという不変の法則さえ機能していなかったように思えます。
そうでなければ、月商7桁アピール、という謎の概念は広がらなかったはずです。
まず最初に自分が売れて、それを元に自分がもっと売れる…、という不変の法則に反したものだったからです。
まさにその業界の中で自分の起業の舵を切ることは、本当にメンタル的にやさしいものではありませんでした。
人は大きな渦の中に入ってしまうと、思考が停止します。
- コミュニティの中で売る当たり前?
- 高額商品を売ることの当たり前?
- お茶会を有料で開く当たり前?
- 講座の無断録音や撮影の当たり前?
- やりがい搾取の当たり前?
- 意味不明なキャッチコピーの当たり前?
この大きな渦が終焉を迎え、多くの人は頼るものを失い、またある人は、自分で思考をする余裕を再び持てるようになってきているのかなと思います。
36歳。2018年に向けてやりたいこと

36歳の誕生日を迎え、そして2018年に向けて、私がやりたいことは3つあります。
- 1つ目は個人の枠を超えて、事業を組織化すること
- 2つ目は自分の専門領域を特化させていくこと
- そして3つ目は、その専門分野で出版をすること
それぞれを詳しくお話させてください。
個人の枠を超え、事業を組織化

会社として法人設立をしたいというよりも、フリーランス的な枠を超えた【チームランス】の結成のイメージです。
個人でこれまで提供してきたことを拡大させるために「自分でもできるけど、自分よりももっとうまくできる人」に任せることを考えています。

その中でも特に目玉は、大崎博之と一緒に新規事業を立ち上げることができるサービス。
大崎の集客リソースであるSNSやメルマガ、LINE@を上手に使って自分たちの認知を広げつつ、お互いにwin-winを作りだせるような、
そういった自らの手でベネフィット(受益)を取りに来る受講生を増やしたいなと思っています。
イメージはホリエモンさんの、HIUオンラインサロンの理念。
勉強とかそういう感じではなく、全力で実践的に人生を楽しもうというラウンジなので、払った額以上のベネフィットを得ようと必死に主体的に参加して欲しい。
専門領域を特化させる

私は2015年の4月に正式に独立して以来、実は明確なポジションを作ったことはありませんでした。
起業コンサルタントという大枠の中で、その時々のニーズに合わせ企画を打ち出すという方針を取っていました。例えばこれまでを例に挙げると、
- 強み発掘家
- 役割の覚醒セッション
- 売上コントロール
- セルフマーケティング
- コアコンテンツの発掘
- ワードプレス集客
- 本質起業
という具合です。
その背景には、起業というのは人によって無限のやり方が存在するので、一つのノウハウに当てはめるなんてナンセンスだと思っていたからです。
ですが、より高確率に、より完成度の高いサービスを打ち出すために専門領域を絞り込もうと考えています。
専門領域の導き出し方としては、これまでの実績でもっとも貢献度の高い専門技術に特化させるという方法を考えています。
それでいくと私は【オンラインでの講師ビジネス】を指導する分野に強いと思っています。
英語やビジネス、ハンドメイド、ヨガ、話し方、などなど。オンラインで伝えられるものごとはたくさんあります。
ブログやSNSがそもそもオンライン上のプラットフォームなのだから、サービス提供もそのままオンラインで完結させる方が利益率も高く、より自由な働き方だと私は考えています。
この手法、ノウハウを自分で構築してきたからこそ、茨城という田舎暮らしのままで起業を継続できてきたと思っています。
今後の継続コンサルティングは、この専門領域に絞っていく予定です。
専門分野で出版する

これはそのままです。
オンライン上の講師として働くをスタンダードにする、をテーマや切り口に考えています。
ある意味で、出版のために専門領域を特化させようと思い始めた部分も一部あります。
もちろん印税目当てなどではなく、マーケティングツールとしての出版を目論んでいます。
36歳の大崎をまとめると…

後悔しない1年にしたい。
それが一番の願いです。
今の自分のままで、得たい結果をダイレクトに受け取っていい。細分化と、ひとつ下の層の目標を達成してから、改めて本来のゴールを目指す、というのは逆算とは違う。そのちぐはぐの原因は、今のままの自分では本当に欲しいもの受け取れないという誤った現実の見方、世界観が原因。
— 大崎博之(ヒロさん) (@H_Yuki2014) 2017年10月23日
私は「愛あるつながり」と「ワクワクの追求」という2つの柱が起業メンタルを支えてくれています。
つまり、誰かとのつながりを感じられない起業ライフは意味がないし、ワクワクしない働き方だったら起業である必要すらない。
だけど2017年までの2年半は、そこの壁を越えきれていなかった。
本当はもっともっと見たい世界がある。
その世界、得たい未来、成果を取りにいって良いはずなのに、それを制止する自分がいた。
「事業を組織化するなら、まずは売れる土台を作り、信頼できる仲間を見つけ、段階を踏むことで…」
というような余計なステップを間に挟もうとしていた。
本当はダイレクトに欲しいものを取りに行っていい。
結婚して幸せになりたいなら、理想の結婚相手を探せばいい。それなのになぜか、まずは痩せてキレイになってから、という前置きを多くの人は用意する。
そうやって欲しいものを取りに行かない姿勢は逆算でも細分化でもなく、ただの弱気。自信のなさ。
その現実に何度も直面してきたからこそ、起業バブル・起業ブームが去って、ホンモノだけが生き残ることが当たり前になるからこそ。
本当にやりたいことで、本当に貢献し尽せることで、本当に愛あるつながりを感じながらワクワクできる仕事で、36歳を、2018年を駆け抜けていきたいと思っています。
これからまた1年、どうぞよろしくお願いします。
不定期ですが、メルマガを発行しています。
誰に向けて……というと難しいのですが、一度こちらのバックナンバーをご覧ください。もしピンときた方は、下記のフォームから無料登録ができます。ぜひご活用くださいませ。